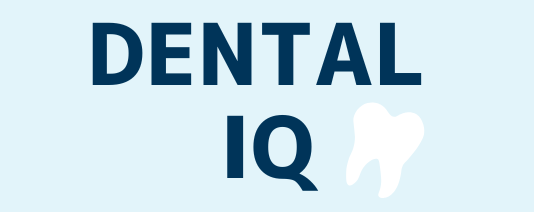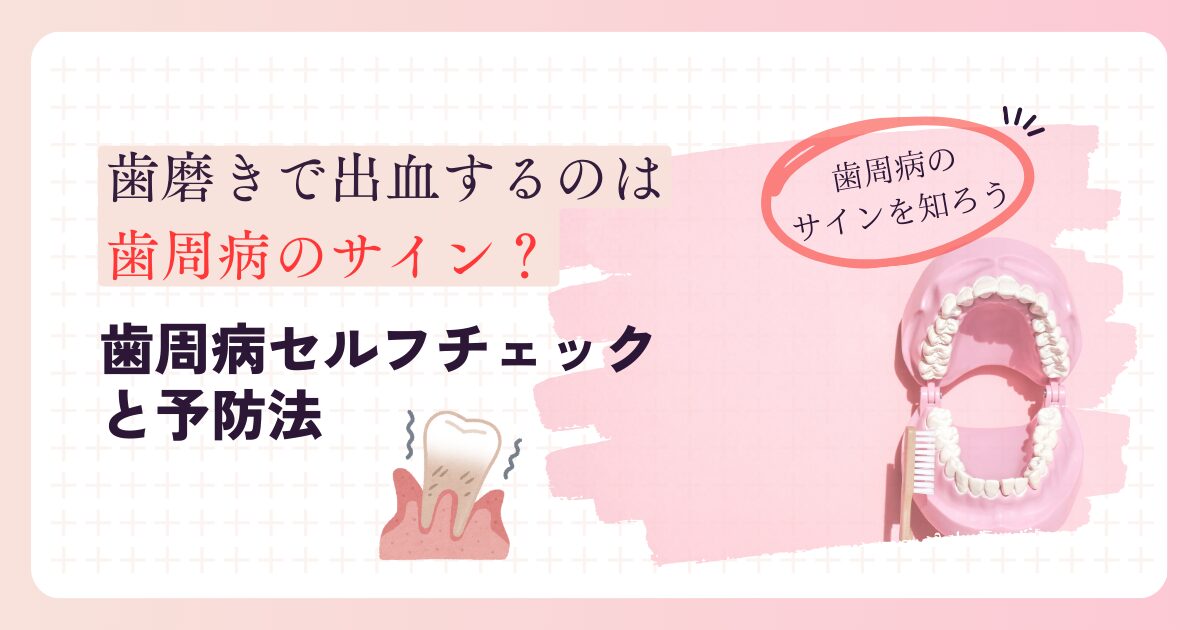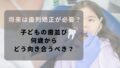はじめに
「歯を磨くと血が出る」「最近、口臭が気になる気がする」
それは、もしかすると“歯周病”になっているサインかもしれません。
歯周病は、日本人の成人の約8割がかかっていると言われるほど身近な病気です。
しかし、初期段階では自覚症状が少なく、気づいたときには進行していた…というケースも多いのです。
この記事では、歯周病のセルフチェック方法と予防のコツを紹介しています。ご自分の歯ぐきの状態を知ることで、早めの対策が可能になります。ぜひ参考にしてみてください。
歯周病とは?虫歯と何が違うの?
歯周病(ししゅうびょう)とは、歯を支える歯茎や骨が炎症によって破壊されていく病気です。虫歯は「歯そのものが壊れる病気」ですが、歯周病は「歯を支える土台(歯周組織)が壊れる」という違いがあります。進行すると、歯がぐらぐらしたり、最悪の場合は抜歯が必要になることもあります。
歯周病の主な原因とは?
歯周病の主な原因は、歯の表面に付着する「プラーク(歯垢)」と呼ばれる細菌のかたまりです。プラークが歯と歯ぐきの境目にたまると、細菌が炎症を引き起こし、さらに炎症が広がると歯肉炎から歯周病へと進行することがあります。放置すると、歯を支える骨にまで影響し、最終的には歯を失うリスクも高まります。
歯周病を悪化させる要因
歯周病の進行を早めてしまう要因として、以下のようなものが挙げられます。
喫煙
喫煙している方は、していない方に比べて歯周病が進行しやすく、治療効果も出にくい傾向があります。タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素が歯ぐきの血流を悪化させ、酸素や栄養が届きにくくなることで免疫力が低下します。その結果、炎症が治りにくく、歯周病が悪化しやすくなります。また、喫煙によって歯ぐきからの出血が少なくなるため、初期症状に気づきにくい点も問題です。さらに、ニコチンはコラーゲンの産生を低下させるため、歯周組織の修復力が落ち、治療の効果も得にくくなります。
歯ぎしり・食いしばり
就寝中の歯ぎしりや日中の食いしばりは、歯や歯ぐきに過剰な負担をかけ、歯周組織にダメージを与えます。強い力が加わることで歯を支える骨や歯ぐきが弱まり、歯周病が進行しやすくなることがあります。さらに、歯が欠けたりヒビが入る原因にもなり、知覚過敏や噛むときの痛みにつながることもあります。
不規則な生活習慣
睡眠不足や偏った食事、過度なストレス、過労などの不規則な生活習慣は、免疫力を低下させ、歯周病を悪化させる要因になります。体の抵抗力が落ちると歯ぐきの炎症が治りにくくなり、細菌感染に対する防御機能も弱まります。
糖尿病などの全身疾患
糖尿病は歯周病と密接に関係しており、お互いに悪影響を及ぼすことが知られています。血糖値のコントロールが不十分だと免疫力が低下し、歯ぐきの炎症が治りにくくなります。その結果、歯周病が進行しやすくなるだけでなく、歯周病の悪化が血糖値をさらに上げてしまう悪循環が起こることもあります。
【歯周病セルフチェック】あなたはいくつ当てはまる?
以下のチェックリストで、あなたの歯と歯ぐきの状態を確認してみましょう。
3つ以上当てはまる場合は、歯周病の可能性があるため注意が必要です。
【歯周病セルフチェック】
- 歯磨きのときに歯ぐきから血が出る
- 朝起きたときに口の中がネバつく
- 歯茎が赤く腫れている
- 以前より歯が長くなった(歯ぐきが下がった)気がする
- 歯と歯の間に食べ物が挟まりやすくなった
- 口臭が気になる・人に指摘された
- 冷たい水でしみる(知覚過敏)
- 歯がぐらぐらする感じがある
- 歯ぎしり・食いしばりの癖がある
- 歯科医院に半年以上行っていない
- 口で呼吸をしていることが多い
- 歯並びが乱れていて歯磨きが難しい
歯周病を予防・改善するためのポイント
①丁寧なブラッシングを習慣に
歯周病予防の基本は、原因となるプラーク(歯垢)をしっかり除去することです。1日2〜3回、歯と歯ぐきの境目を意識しながら、力を入れすぎず丁寧に磨くことが大切です。特に、1本ずつの歯を意識して磨くと、より効果的に汚れを落とせます。また、歯ブラシの毛先が開いてしまうとプラーク除去の効果が低下するため、清潔さを保つためにも1カ月に1回を目安に交換しましょう。
②歯ブラシに加えて補助用具を活用する
毎日の歯磨きに加えて、フロスや歯間ブラシなどの補助用具を取り入れることで、歯と歯の間にたまりやすい汚れを効果的に除去できます。特に歯周病は「歯と歯の間」から進行することが多いため、1日1回は取り入れるのがおすすめです。
また、奥歯や細かい部分に届きやすいタフトブラシは、磨き残しを減らすのに役立ちます。さらに、抗菌成分を含むマウスウォッシュを併用することで、口腔内をより清潔に保つことができます。
③定期的な歯科検診
症状がなくても、半年に1回の歯科検診とクリーニングを受けることで、早期発見と専門的なケアが可能になります。検診では歯ぐきの状態をチェックし、普段の歯磨きでは落とせない歯石や着色汚れもプロの手でしっかり除去します。また、歯周病のリスクが高い方や症状が進行している方は、1〜3カ月ごとの短い間隔でメンテナンスを行うことで、より健康な口腔環境を保ちやすくなります。定期的な受診は、歯を長く守るための大切な習慣です。
④生活習慣を見直す
歯周病予防には、毎日の生活習慣を整えることが大切です。食事や睡眠、呼吸などを意識して、健康なお口を保ちましょう。
- 栄養バランスの良い食事
- 睡眠をしっかりとる
- ストレスをためない
- 鼻呼吸を意識する(口が開きっぱなしになっていないか)
- 禁煙を検討する
歯周病は体の健康にも影響することがある
進行した歯周病は、口の中だけでなく全身の健康にも悪影響を及ぼすことがわかってきています。歯周病はお口の中だけでなく、全身の健康にも深く関わっています。近年の研究では、進行した歯周病がさまざまな病気のリスクを高めることが明らかになっています。例えば、次のような健康への影響が出るケースも報告されています。
- 糖尿病の悪化
- 誤嚥性肺炎のリスク増加
- 心筋梗塞や脳梗塞のリスク上昇
- 妊娠中の早産・低体重児出産
まとめ
歯周病は自覚症状が少ないまま進行することが多いため、日頃からのセルフチェックと予防がとても大切です。歯ぐきの腫れや出血など、気になるサインがある場合は、早めの対策を心がけましょう。お口の健康は、一生を支える大切な資産です。未来の自分のためにも、今日からできるケアを始めることで、歯と歯ぐきを長く健康に保つことにつながります。