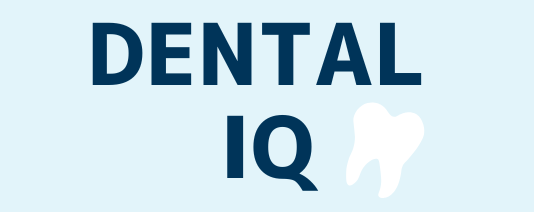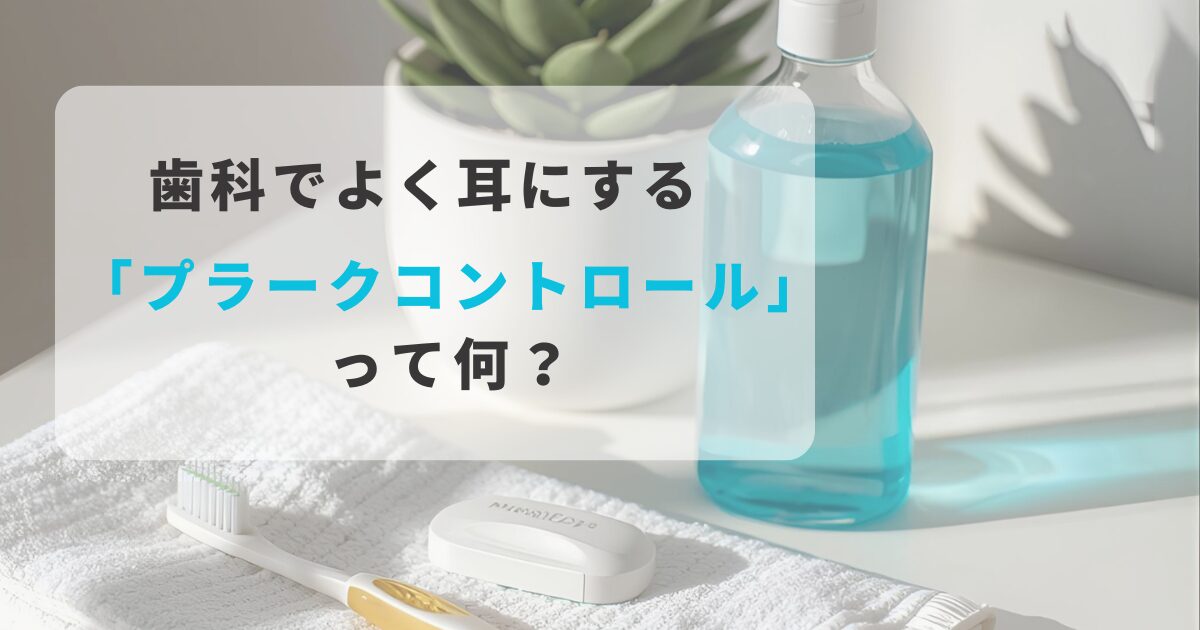はじめに
歯科医院で「プラークコントロール」という言葉を耳にしたことはありませんか?
プラークとは歯の表面に付着する細菌のかたまりで、放置すると虫歯や歯周病を引き起こす原因となります。この記事では、プラークの正体、プラークコントロールの方法、歯科医院で受けられるチェック方法、そして放置するリスクまで詳しく解説します。
1. プラークとプラークコントロールの基本
プラークとは?
プラークは、食べかすや糖分を栄養にして口内細菌が増殖した、白く柔らかい粘着質の汚れです。唾液で流れず、歯ブラシで除去しない限り付着し続けます。放置すると細菌が成熟し、虫歯や歯周病を引き起こす原因となります。
プラークコントロールとは?
プラークコントロールとは、プラークを効果的に除去・管理するための取り組みです。
歯科医院では専用の染め出し液でプラークを可視化し、プラークスコアを算出します。目標は20%以下で、10%以下なら非常に良好な口腔環境です。
2. 歯科医院でわかる!プラークの状態とスコア
プラークスコア
プラークスコアは、歯にどれくらいプラークが付着しているかを数値で表したものです。
- 理想的:10%以下(非常に良好な状態)
- 目標:20%以下
- 要注意:30%以上 → セルフケアや歯科での改善が必要
プラークが付きやすい場所
人によって磨きにくい箇所や、噛み癖、歯並びなどが異なるため、プラークがつきにくい箇所も異なります。歯科で、効率的なブラッシング指導を受けることで現在の歯磨きの改善点や、プラークの残りやすい場所を教えてもらうことができます。
- 歯と歯ぐきの境目
- 歯と歯の間
- 補綴物(被せ物や詰め物)と歯の境目
- ブリッジの人工歯の隙間
- 奥歯の後ろ側
- 前歯の裏側
- 親知らず
- 上の奥歯の頬側
- 歯石がたまっている場所
- 生え変わりの歯
- 奥歯の噛む面の溝
- 歯並びが悪い部分(突出している・重なっている・凸凹している・隙間が開いているなど)
3. 効果的なプラークコントロール方法
歯磨きで毎日コントロール
- 歯ブラシは毛先を歯と歯ぐきの境目に45°の角度で当てる
- 力を入れすぎず、小刻みに動かす「バス法」がおすすめ
- 1回あたり2〜3分以上を目安に、毎食後磨く習慣
- 寝る前は特に丁寧に、1歯ずつ磨く
- フロスや、抗菌作用や虫歯予防効果のある歯磨き粉やマウスウォッシュを取り入れる
補助清掃用具の活用
- デンタルフロス:歯間のプラーク除去に効果的です。一度使うと、古い汚れの蓄積に驚く方が多いです。
- 歯間ブラシ:歯ぐきが下がった部分やブリッジ周囲に効果的です。歯ぐきが下がっている場合は歯周病があるため、より丁寧なプラークコントロールをするために歯間ブラシは必須アイテムです。
- タフトブラシ:奥歯や重なった歯列、親知らずや奥歯の届きにくい箇所、歯と歯ぐきの境目を丁寧に磨くのに便利です。1歯ずつ磨くことで磨き残しをより減らすことが可能です。
フッ素や洗口液の併用
フッ素入りの歯磨き粉を使うことで歯質を強化し、虫歯になりにくい状態をつくることができます。さらに、抗菌作用のある洗口液を併用することで、お口の中の細菌の増殖を抑え、プラーク(歯垢)の付着を予防しやすくなります。ただし、効果を高めるためには、まずしっかりとブラッシングでプラークを除去したうえで使用することが大切です。
4. プラークを放置するリスク
歯石の沈着
プラークは長時間放置すると唾液中のカルシウムと結合し、歯石に変化します。
歯石は歯ブラシでは取れず、歯科医院でのスケーリングが必要です。
虫歯リスクの上昇
プラーク内の細菌は、食べ物に含まれる糖を分解して酸をつくり、その酸が歯の表面(エナメル質)を溶かします。これにより初期虫歯が進行しやすくなり、放置するとより深刻な虫歯へと悪化する可能性が高まります。
歯周病の進行
プラーク内に潜む歯周病菌は、歯ぐきに炎症を引き起こし、歯肉炎や歯周病の原因となります。症状が進行すると、歯を支える骨が少しずつ破壊され、最終的には歯がぐらついたり、抜け落ちてしまうこともあります。
5. 歯科医院で受けるプロフェッショナルケア
PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)
専用の機器を使い、歯ブラシでは落とせないバイオフィルムやプラークを徹底的に除去します。歯面を滑らかにすることで、プラークの再付着も防ぎます。
定期的なメインテナンス
定期的なメインテナンスを受けることで、プラークスコアを継続的にチェックし、虫歯や歯周病を早期に発見できます。また、患者様一人ひとりの歯並びや磨き癖に合わせた適切な歯磨き指導も行うため、より効果的なケアが可能です。こうした継続的な管理により、プラークスコア20%以下という目標を維持しやすくなります。
6. よくあるQ&A|プラークコントロールについて
- Qプラークコントロールはどのくらいの頻度でチェックすればいいですか?
- A
健康な方は3〜6か月に1回の歯科検診がおすすめです。
プラークスコアが30%以上の方や歯周病リスクがある方は、1〜2か月ごとのチェックが効果的です。
- Q染め出し液は自宅でも使えますか?
- A
はい。市販のプラーク染め出し液を使えば、自宅でも磨き残しを可視化できます。
ただし、歯科医院での染め出し検査の方が精度が高いため、定期的に歯科でのチェックも取り入れると理想的です。
- QPMTCはどれくらいの間隔で受けるべきですか?
- A
健康な方は半年に1回、リスクが高い方は3か月に1回が目安です。
プラークが多く付着している方は、短い間隔で受けることでプラークスコアを20%以下に近づけやすくなります。
- Qプラークスコア10%以下はどうすれば達成できますか?
- A
歯ブラシだけでなく、フロス・歯間ブラシ・タフトブラシを活用するのが効果的です。
さらに、歯科医院での磨き残しチェックとブラッシング指導を組み合わせることで、効率的に10%以下を目指せます。
- Q毎日磨いているのにプラークスコアが下がりません…
- A
毎日磨いていても、歯と歯ぐきの境目や奥歯の裏、歯間などの清掃が不十分だったり、力を入れすぎて毛先が寝てしまうことでプラークが残る場合があります。歯科医院でブラッシング指導を受けると改善することが多いです。
まとめ
プラークコントロールは、虫歯や歯周病を防ぐために大切な習慣です。毎日の正しい歯磨きとデンタルフロスなどの補助清掃用具を活用し、さらに歯科医院での定期的なチェックやクリーニングを組み合わせることで、口腔内を健康に保てます。まずは一度、歯科医院でプラークスコアを確認し、自分に合ったケア方法を見つけることから始めましょう。